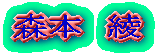初めてビルマを訪れたのは、ほんのきまぐれだった。一九九四年、当時私は東南アジアをカメラ片手にほっつき歩き、ついでにビルマに立ち寄ったという感じだったのだ。しかし、訪ねた東南アジア一〇カ国の中で一番強く私の心を捉えたのはどこでもない、ビルマだった。
ビルマのどこに魅了されたのか、それはこの国に暮らす人々の優しさだ。道で地図を見ていると、向こうから「どこへ行きたいの?」と声をかけてきてくれ、丁寧に教えてくれた。時には案内までしてくれた。バスに乗れば席を譲り合う光景が繰り広げられる。何かを期待した親切心ではなく、皆ニコッと微笑んで立ち去るのだ。そんな些細な事柄が、私の胸に響いた。日本人としての自分は親切にされることに慣れておらず、自分が特別な人なのか、と勘違いしそうだった。人間は優しい動物だと教えてくれたのは、彼らの生きざまだった。居心地のいいビルマに九七年から一年間、ビルマ語留学をするまで私はのめりこんでいった。
ロンジーと呼ばれる筒状の腰巻き布をまとい、約二〇〇円ほどでオーダーしたブラウスを着て、ぞうりを履き典型的ビルマスタイル でバッチリ決めていた。時には「タナカー」と呼ばれる樹の皮を水ですりおろした汁を顔に塗りたくった。これがスーッと涼しく気持ちがいいのだ。日焼け止めと美白効果があり、香水の代わりにもなる優れもの。これがビルマ独特の化粧法なのだ。油っぽい食事にも慣れ、うまく右手でご飯を食べれるようになった頃には日常会話に困らない程度のビルマ語ができるようになっていた。すっかりビルマ人化した私のことを日本人だと誰も気づきはしなかった。
ビルマは一三五もの民族が暮らす多民族国家なのだ。私のことをビルマ語の下手な少数民族だと思っていたようだ。ある時タクシードライバーと値段交渉していると、横から「もっとまけてやれ」と助け舟を出してくれたおじさんがいた。田舎から出てきたと思ったようだ。私が日本人だから親切にしてくれるのではなく、どこの国の人であろうと彼らは親切なのだ。
留学を終えても一年に一度、ビルマにやって来る私に「そんなによい国ですか?」とエーエーさん(39才・女性)はいつも聞く。どこの国でも言えることだが、良い人もいれば悪い人もいる。嫌な思い出も確かにある。それら全部をひっくるめて私はこの国が大好きだ。「人間は愛を送り合って生きてるんだよ」そんなことをエーエーさんに言われたことがある。日本で愛なんて言葉を言われたら恥ずかしくってしょうがない。でもビルマで聞くこの言葉はなるほどなと思ったものだ。見返りを期待しない彼らの優しさを理解したような気がした。
ビルマ人口の八五%以上が敬虔な仏教徒だからか、ビルマでは生活の中にブッダの教えが浸透している。首都ヤンゴンでも町は緑であふれ、大樹は暑いこの国に涼をつくりだしている。「木を育てる」──これは功徳の一つなのだ。そして、いつでも咽が乾けば水が飲めるよう、木の下などに水壷が置かれてある。日本では毒が盛られているかもしれないと思ってしまうだろう。そのことを水壷の管理をしているおばさんに話してみた。おばさんは考えたこともない!と目をむいて「水功徳といってね、素晴らしい行いなのよ」と誇らし気に語ってくれた。
早朝、僧侶の托鉢を知らせる鐘が鳴り響く。檀家はぞうりを脱ぎ、ご飯やおかずを僧侶の黒い器に入れる。ビルマはこんな調子で一日が始るのだ。そして一年は仏教行事で回っている。新年を祝う水かけ祭り、ブッダが悟りをひらいた日、僧院にお布施をする日……若いカップルのデートがパゴダ(仏塔)なんてあたりまえ。私の友人は僧院で出逢った男性と結婚したのだ。石を投げればパゴダか僧侶に当るほど、そこいらに仏教を感じることができるだろう。テレビのニュースや新聞のトップ記事が「軍政府の幹部が僧院に多額のお布施をしました」なのだから。他にニュースはないのか?と突っ込みたくなるほどだ。
その2へ続く