チュンポン市内から河口までの当時の道路の状況。象の力を借りなければならなかった
日本軍が上陸時に撒いたビラ。「アジアの敵、英国をやっつけろ」「長い間英国に抑えられてきたタイは日本と協力すべきです。日本はタイの発展を望んでいる」という言葉が記されている。国旗はタイの国旗。
(タイ国立公文書館所蔵)
1941年12月、日本軍がマレー半島に上陸したとき、タイ政府が訪問・調査したときの珍しい写真。上陸後、日本軍を訪問したタイ代表。日本軍はタイの寺院や学校を無断で宿舎や病院にしていた
(タイ国立公文書館所蔵)
瀬戸正夫さん
2001.4.29
バンコク
インペリアル・クィーンズ・ホテルで

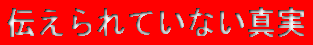
五十嵐勉●おかげさまでアジアウェーブも一〇〇号を重ねることができました。読者の皆様にも深く御礼と感謝を申し上げますと同時に、「東南アジア通信」から「アジアウェーブ」と、この報道活動の生みの親の一人でもある瀬戸正夫さんにもあらためて御礼申し上げたいと思います。ありがとうございました。
瀬戸正夫■おめでとうございます。
●アジアウェーブの前身である「東南アジア通信」は朝日新聞アジア総局(当時バンコク支局)顧問の瀬戸さんのご支援でできたわけですが、おかげさまで一〇〇号、「東南アジア通信」からの通刊では一二〇号に辿りつくことができました。
一〇〇号を記念して、今年は太平洋戦争・開戦六〇周年でもありますので、開戦当時も南タイの日本軍上陸地にいらっしゃった瀬戸さんに、当時のことを振り返っていただきながら、戦争と日本のことをいろいろお聞きしたいと思います。それは、ある意味で、このアジアウェーブの発行の意志の根幹をなすものにも繋がっていますので、それもあらためて振り返ってみることにもなると思います。
また長く外国から見てきた日本の姿はどのように映るか、タイから見た日本、日本人について、いろいろ語っていただき、一つの指針が得られればと思っています。一度では収まらず、シリーズのロングインタビューになると思いますが、瀬戸さん、どうぞよろしくお願いします。
瀬戸■私もいろいろ振り返ってみたいと思います。どうぞ何でも聞いてください。
●瀬戸さんの生い立ちと日本の開戦諜報活動
●瀬戸さんは昭和六年プーケット生まれだそうですね。
■そうです。プーケット生まれです。父は医者で、僕の母はプーケット島にいたタイ人です。でも、父が引き取って父と継母の手で育てられました。幼い頃はソンクラーにいましたが、バンコクに移ってからはバンコク日本人学校に通ってました。一九四一年の開戦もバンコクにいたときで、バンコク日本人学校の生徒は全員ガンジス丸に乗せられて避難させられたのをよく憶えています。
父はある時期から医者の仕事よりも、日本軍がマレー半島に上陸するというので、諜報活動をしていました。
●諜報活動は、どんなことをしていたんですか。
■一九三〇年代の終わり、日本が南進政策を決定するころから、特にマレー半島に上陸してイギリスの軍事力を駆逐するということが日本軍の一つの大きな課題になりました。イギリスの拠点シンガポールを攻略することが最終目標だったわけです。それでどこから、どのようにイギリス軍を攻略していくかが重要な軍事課題となりました。そのため、マレー半島の詳しい現地情報がどうしても必要になったわけです。それに南タイに詳しい父が協力したわけです。当時ソンクラーに日本領事館ができて、ここを中心に活発に諜報活動が行なわれていました。
日本軍は直接マレーシアに上陸せず、タイ領に無傷のまま上陸してそのまま南下するという戦略を準備していました。父は日本軍が上陸するのはどこがいいか、上陸海岸の情報を集めて送ってたんです。海の深さを計ったり、周囲のタイの村落の状況を調べたり、綿密な調査をしていましたね。日本軍の上陸に備えて、いろんなことをやってました。僕もいっしょに釣りに行って、僕のほうは釣りしてましたけど、父は船の上から糸をたらして海の深さを計ってました。父は全部それをノートに取ってきちんと記録してました。そのときはなぜそんなことをしているのかわからなかったですね。父が測った地点は、ほとんど日本軍が上陸しています。
日本軍が上陸した朝、父は突然軍服に着替えました。父は日本軍上陸後は、出世して、いろんなことをやって、マラッカの警察署長もやっていましたね。
●日本軍の上陸
●日本軍がどうやって上陸したか、現代の日本人はほとんど知らないでしょうね。
■開戦時、日本軍とタイ軍で衝突があって戦争をしたということは、日本人はほとんど知らないでしょうね。無血上陸のように書いてあるんじゃないでしょうか。マレー半島に上陸したということさえ、今の人たちには知らない人も多いでしょうけど。タイの教科書にははっきりと日本は敵前上陸したと書いてあるんですよ。でも日本の資料はどこを調べても敵前上陸したとは出てこない。実際にはタイ軍と日本軍は衝突してタイ軍も相当の数が死んでいますし、日本軍も死んでいるんです。でも日本側の記録には平和進駐とか、平和交渉としか出てこない。隠されているんですね。
戦争が勃発したとき、ナコンシータマラートでも、大南公司でスパイ活動をしていた連中ですけれども、それ前にスパイ行為をしていて、タイの警察に六人逮捕されて殺されています。銃殺です。どういう理由で、どうやって殺されたか、うやむやに葬られてしまっています。
それからもう一つだいじな事実があります。日本軍は平和進駐の形でタイを通過させてくれという条件で、タイと日本軍は停戦になった。だけど十二月八日の夕方六時、普通ならタイの国歌が放送される時間です。でもそのとき、タイの国歌ではなく、「君が代」が流れたんです。タイ全土に。それは何なのか。故意にやったのか、事故なのか。僕はやっぱり、故意にやったんだと思うわけです。日本がもう占領したんだというような気持ちでやったのかと。タイが自分からそんなことをやるはずがないですから。日本軍の圧力でやらざるを得なかったと思うんです。言われるとおりにやるしかなかったのかもしれない。その当時のタイの国民の気持ちはどんな気持ちだったろうか。そういうことを日本人は考えたことがあるんでしょうか。
バンコクの場合はそんなに問題はありませんでしたけど、南タイの方は日本軍が上陸してきて、タイ軍との間に戦闘があってたいへんなことになったわけです。上陸と同時に日本軍が家の大事なものはみんなかっさらっていっちゃうし、きれいな女の人は強姦されるし、反対すれば殺されちゃうし……。そういう被害にあった人や、それを見てきた人たちはいまはみんな七十代、八十代になっています。その人たちはいまだに毎年十二月八日の午前中、上陸した地点で、慰霊祭をやってるわけですよ。両親がもう亡くなっているところもあるでしょうけど、それがいまだに忘れられない。毎年やってるんです。そういうものは、民族の痛みとして忘れられないわけですよ。日本の人に、他人の痛みを自分の痛みとして感じることをしてほしいわけですよ。
日本も日本の痛みがあると思うんですね。日本は原爆慰霊祭を毎年やっているけれども、日本もやはり戦争の痛みを思い出して、それを繰り返さないことで癒そうとしていると思うんですね。でもその思いは、日本だけじゃないですよ。世界中忘れてないですよ。おそらくフィリピンだってどこだって、シンガポールだって、そういう気持ちを抱いている人は多いと思う。韓国も特にね、台湾も。あまりにアジアのそういう感情を無視しすぎている。ひどいことをしたという憐れみの気持ちや、反省の気持ちが乏しくて、歴史を振り返って、それを受け止める意志が失われている。歴史を受け止める意志が感じられない。それが今の日本人の無責任さや若い人のひ弱さにつながっていると思いますよ。
●バンブァトン日本人収容所
●終戦間際の昭和二〇年頃、連合軍の爆撃で、工場なんかが全部爆撃でやられてしまいましたね。終戦になって、それまで日本が占領的な立場にいたのが、逆転して、みな敗者になってしまった、その一八〇度変わってしまったものも経験されているわけですよね。
■日本人は皆バンブァトンの収容所へ入れられて、キャンプ生活を送ったわけですね。父は戦犯で捕まって、シンガポールのチャンギー刑務所に入れられました。幸い、住民の歎願で出ることができて、日本へ帰国できましたけど、父は僕も継母もおいて、一人で日本へ帰ってしまいました。冷たかったですね。
バンブァトンのキャンプは不自由な面はありましたけど、食糧や生活必需品は配給されたので、全然苦労なかったですよ。遊んでばかり。金銭問題は全然知らなかったです。お金のない生活をしてたので、お金が大事だってこともわからなかったし。キャンプ出てからです、たいへんだったのは。自分でお金を稼ぐようになって。継母の分まで稼がなきゃならなかったんで……
●それまで、瀬戸さんはほんとうのお母さんのことを知らなかったんですか。
■知りませんでした。でも何か冷たいので、うすうすは気づいてましたけど、ほんとうのことを知ったのはあとになってからです。継母に生活力がなくて、一五歳の僕に全部かぶさってきちゃったんです。バンブァトンから出て、ドーンと生活がのしかかってきて、何でもやりましたよ。金魚売りや、バーのボーイや、生きていくためには何でも……
●日本から拒否された国籍
●瀬戸さんは日本に帰らなかったんですか。
■父がどうなったかわかりませんでしたし、呼んでもくれませんでしたしね。捨てられたんでしょうけど。それと、日本人として認めてくれなかった。拒否されました。日本に帰りたくても、帰りようがないですよね。日本人としてもはっきりと拒否されましたからね。
バンブァトンキャンプを出て、昭和二七年ころだったかな。講和が結ばれてこちらに日本大使館ができてから、「日本人は書類を持って出頭してください」という知らせが来たんですよ。日本人会から。それで日本大使館へ行ったんです。僕は書類といっても何もない。バンブァトン・キャンプで発行されたタイに居住していもいいというタイの証明書とキャンプでもらった日本大使館領事部の僕の父と母の名前が入っている証明書があるんですよ。それを持ってたんですけどね。そしたら戸籍抄本を取り寄せてくれって。それで僕は戸籍抄本を取り寄せた。ところがそれに僕の名前が入ってなかった。それで日本人として認められないっていうわけですよ。
その戸籍謄本に名が入ってないというだけの理由で、日本人として認められなかった。すべて日本人として育てられたのに、日本人じゃないというわけですよ。
●日本人学校にも行っていたのに……
■日本人学校の場合は、日本人学校から「瀬戸正夫は日本人だから日本人学校へ通わなければならない」という手紙が来たわけです。だから僕は日本人学校へ入ったわけです。当然日本人としてすべて処理されていると思ったわけです。
●日本人でないと拒否されたときの思いは、どんなでしたか。
■それはもう怒りましたよね。僕は。でも怒るにしてもそれをだれにぶつければいいのかわからない。日本の政府の役人は、ただ一言だけ。「戸籍謄本に名前がないので」というだけ。「法律で決められていますので」それだけでした。知っている者同士だから向こうもきがねしちゃって、「悪いけど」って言われて。「それはもうわかった」と。その人に怒るわけにはいかないでしょ。その人は大使館の領事部の担当者だから。お付き合いがあるし。「悪いけど瀬戸さん、こういう事情なんだよ」と。
ペーパー主義の日本は何もしてくれなかった。父の子なんだし、日本人として育てられ、教育されたわけだから、ちゃんとした保証が得られるはずなんだけど、形式主義の日本は何もしてくれなかったわけです。
●瀬戸さんは当時日本の国籍だけでなく、タイの国籍も持っていなかったとお聞きしていますが。
■日本が国籍をくれなかったとき、僕はもちろんタイ人でもなかったわけです。自分の帰属がどこなのかわからなかった。僕はいったい何人で、どこへいけばいいんだろう──と苦しみました。三〇歳まではずっと、国籍がなかったんです。それも僕が好んでやったわけではないですからね。父に聞いていたのは、タイの役所にも届けてあるし、日本の領事館にも届けてあるということだったんですけど、実際見たら、どこにもないんですよ。生まれがプーケットでしょう。プーケットなんて小さな島で、当時のことだから、役所でどうしたか、もう残っていないわけですよ。
第一自分の母親も最初はわからなかったですよ。で、一人残されて、最終的に自活していきましたけど、母親のことは知りたかった。生みの母親のことをどうしても知りたかった。それで、新聞広告に出したんです。そのときは反応がなかったけども、しばらくしてからあった。やっと見つかった。それでプーケットに行ったんですよ。会ったときは、それはもう感激しました。向こうも泣いて、感慨無量でした。この人から生まれたんだと。もう一目ですべてがわかりますよね。生みの親は何も言わないでもすべてわかります。自分のルーツをやっと確認できたわけです。
でも戸籍の問題はそれで解決しませんでした。プーケットもまずはじめに警察へ行って、出生届けがないっていう証明をもらって、それで市役所へ行って取ろうとしたんですが、市役所もだめだったんです。市役所で「裁判所へ行きなさい」と言われました。それで本当の母と地方裁判所へ行った。ところが僕はバンコクで育って、バンコクに住民票があるから、バンコクへ行かなければだめだと言われた。で、結局どこへ行ってもだめなんですよ。無駄でした。僕は何者なのか、無国籍のまま一生終わるのかと虚しくなりましたね。
で、僕が最終的に取った手段というのは、タイの警視庁に捜査係というのがあって、そこへ行ったんです。国籍捜査係というのがありました。そこへ行って、「私は何者でしょう。国籍は何でしょう」と申し立てて、調べてほしいと頼んだわけです。それで初めて、光明が見えてきました。
けっこうかかりましたよ。時間もかかったし、お金もかかった。結局内務省から最終的にタイ人として認められたわけです。内務省から通知が来た。その代わり、兵役に入らなければなりませんでした。
●兵役に就いたんですか。
■就きませんでした。タイの兵役は、一定のお金を払うとそれで済むんですよ。お金を払いました。それでやっとタイの国籍が取れ、タイ人になったわけです。でも、精神的には日本の教育を受けましたから、やはり日本人なのかもしれませんけどね。








