|

アンコール・トムのバイヨン像

アンコール・ワット

「王の沐浴場」スラ・スラン遺跡で演じるパント・マイム「輪廻転生」
写真提供/「アプサラプロジェクト2001」

アンコール・トムの外れで
矢野かずき
バンコク在住
パントマイマー
JVCボランティア・難民定住調査員を経て、
現在バンコクで劇団を主宰
著書「難民キャンプのパントマイム」
トップページへ戻る
|
|
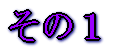
視界は魚眼レンズのそれのよう、真上を見上げたままの私の目のなかには、輝く群青の、亜熱帯の、乾季の蒼穹、視界の周囲からは黒緑の樹々の影たちがその高みに向かって絡まりつつ伸びていた。そしてその前景に、ある遺跡建造物の、壁の落ちた二階があった。
(なぜ降りて来ない?)
見上げたまま発した私の問いに、透明なその貴人は何も答えようとしなかった。
二〇〇〇年十一月のある日、生まれて初めて訪れたカンボジアの町シェム・リアップ。その町の郊外、東京都区内と同じ広さの面積にアンコール・ワットをはじめとし、主要なものだけで二六ヶ所のアンコール遺跡がある。そのなかのひとつ、プリア・カーン。聖剣寺院と呼ばれるその仏教遺跡の石の内陣の一画で、私はその貴人に出会った。
十二世紀末、ジャヤヴァルマン七世によって建立されたこの仏教寺院はアンコール・トム遺跡の西北に位置する。一〇〇メートルはあろうかと思われる参道の両側には石灯篭のようにリンガ(男性器偶像)が並ぶ。上下左右から物言わず迫ってくる石柱の、狭い西の廊の薄闇を腰をかがめながら抜けた後、ぽっかり開けた視界の向こう、東の参道へ続くくずおれた石柱の並びに隠れるように、境内の一隅に美しい建物があった。
アンコール遺跡群のなかでも珍しい、円柱で構成された構造をもつ二階建のその建物は経蔵(ライブラリー)と説明された。苔の黒や乾いた白でぶちぶちに縁取られ、幾本かの蔦を這わせた建物全体はなぜか薄青く緑がかった光をまとっているように感じられ、プリア・カーンの本堂を形作る石とはその質もちがうのかとさえ思われた。基層をなす円柱たちの間隔は狭いが、うるさくはなく、絶妙のバランスをとってどっしりと構えつつも二階が高いためか空間には心地よい軽みとゆとりが生じている。屋根こそ崩れ落ちてなくなっているが、それは石造りの優美な半円形のものであったろう。境内のまわりをめぐる樹々の影が落ちる水濠の、これはその水面を見下ろす位置に建っていたのではないか。いったいどのような人々がこの経蔵に立ち入り、どのような仕草で、どのような言葉を交し合ったのか、そして彼らの目が窓外に見た風景は……。
私はその経蔵のまわりを独り、巡った。
不意にその情感に襲われたのは、経蔵の東の一画に立ったときだった。
視界のなかには誰もいないはずなのに、生々しく何かが動いたように感じられた。物音がしたわけではない。はっきりと私の目が何かの動きを捉えたわけでもなかった。あえて言葉にするならば、伝わってきた気配、としか言いようがない。私は周りを見回した。経蔵の東に、内陣をふちどる壁がめぐっている。その壁の一隅に彫られた一体の女神デヴァターに私の目は吸いつけられた。どう考えても、その場で「動きそう」なものはその彫像しかなかったのだ。しかも、汗と土ぼこりで汚れた私のめがねを通して見るその彫像は、輪郭がおぼろでプルプルと震えているよう、もう一度動いてみせようかと、まるでいたずらのチャンスを待つ小さな人のようなのだ。
枯葉と石くれと雑草が覆う赤い乾いた土の上をたどって私はデヴァターに近づいた。それは、風化と破壊のために細部が形を失ったものだった。地蜘蛛の糸が肩から胸へ幾筋か這い、かすかな緊張を見せて揺れている。しばらく間近に眺めたあと、私はその場を離れてもういちど経蔵のつくる影に入った。気配はまだ続いている。そこから振り返って見たデヴァターもやはり再び動き出すかのようだ。
経蔵の東面は勾配のある数段の階段になって、昇りきったところにはレリーフに覆われた壁があった。それは中央で合わせになっているようで、重い開き扉かとも思われたが一度も開かれたことはあるまいとも感じられた。石の階段は奥行きが狭く、角がもろそうで、ロープや立て札などなんの指示もなかったが、登ることをためらわなければならなかった。私はその正面を離れ、もう一度経蔵の全体が目に入ってくる角へと動き、そして二階を見上げるべく真上に顔を上げた。
貴人と目が合った。
彼(彼女?)は壁のない二階の床のふちにうずくまるように両手をかけ、そこから首だけを出してじっと階下の私を見つめていた。表情のないその顔は白く、頭にかぶるぼやけた輪郭の飾り物の下で目には瞳が感じられない。
私の目には空っぽの廃址しか映っていないはずだ。なのに全身はその透明な誰かとの見つめ合いに凝固した。いま感じているこの視線、私のそれに真っ向からぶつかってくるこの視線はいったい何なのか。沼の水面を伝う粘り気のある波のように寄せてくるその情感はかろうじて私の理性にぶつかって散る。けれども、さっきから感じていた気配、ここらへ向けて強烈に降り注ぎ、壁のデヴァターも動くかと思わせるほどに空間の質を変化させているそのエネルギーは確かにこの経蔵の二階からやって来る。その確信だけは私のなかに重く座り込んだ。
意を決し、私はその場を跳び退くように離れ、経蔵の西面へまわった。
午後の傾いた陽光は樹々や円柱にさえぎられ、一階の石の床は暗いと思えたが、中へ入ってみると照り返しの光でいっぱいだった。外からの印象が「暗い」と思えるほど、この地の陽光と大気の澄明さは事物すべての影のコントラストを強くあぶり出す。枯葉、乾いてはがれた苔、誰かが捨てていったプラスチックボトル、綿ぼこりかと見まごうまでに朽ちた何かの布切れ……。それらが風に吹き去られることなく所々に落ちている。
あの気配の正体、まなざしだけの小さな幽霊のその顔、声か香りか、肌に触れる感触かあるいはそのどれでもないものか。何に出会うかわからない真昼の心細さがある。が、振り返っただけでここを去ることはなおさらできそうになかった。石の円柱の間を私は奥へ、東へ、何者かがいるはずの二階へつながる階段を探してまっすぐに歩いた。そしてすぐに、小さなその遺跡のなかで、私は奥の壁にぶつかった。
見上げると二階の床は数ヶ所落ちてなくなり、そのまま視線を空の蒼に向かって逃がしてやることができる。この遺跡には、空間を斜めによぎっていたはずの階段はもう残っていなかった。この経蔵の二階にとどまる何者かとは、だから決して間近に相まみえることはできないのだった。
陽光にあぶられ、溶樹に解体され、人の欲望に削られ、無感謝に汚される石たち。苔の浸透や爬虫の糞尿、雨、風にさらされる無数の石たち。深い樹林の中にはいまだその存在を観光マップに書き込まれていない遺跡たちが、いつ除去されるかわからぬ地雷に囲まれてうずくまっている。それらの一つ一つが、ここのように、いまだ冒されない血が通うような一隅をもつとすれば……。
豊饒な亜熱帯の樹海のなかで人知れずそこに漂うもの、それは確かに、紛うことなく「情」だ。それは重い乳の滴りのように発され、樹々の幹をからまり登り、陽光をさえぎる枝や蔦や葉の下、森のなかを音もなくひろがりながら、風になびかず、そして突然、宙空へと真っ直ぐに、どこまでとも知れぬ高みへ向かって真っ直ぐに立ち昇って気圏の果てに溶け込んでいく。この地の遺跡たちはいまもなお生きて情を発しているのだ。生きているがゆえに侵され、とどまることなくじわじわと解体される。病を体内に生じ、衰えつつ輝こうとする。樹海のなかの生命の輪廻の多層のなかに、生ける遺跡たちもまた、ある。トンレサップと呼ばれる大湖のほとりの樹海のいたるところから、情ののろしがいくつもあがる。
このような場所で、見て去るだけの者であるなといわれたら……。
聖剣寺院プリア・カーンの一隅に立ち、私はその日、国境を越えて来たことを少し後悔した。
アンコールの遺跡をバックに、地平から月が昇ってくる夕刻、クメール伝統舞踊の舞姫たちとともに無言の劇を演じてみないかと持ちかけられてから三ヶ月が過ぎていた。
(つづく)
(矢野和貴/バンコク在住/パントマイマー)
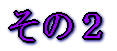
タイの首都バンコクから隣国のカンボジアとの国境までは車で数時間の距離だ。その距離の倍ちかくをフライトは五〇分であっさりと飛翔して、私の体をシェム・リアップの空港へぷいと吐き出す。国境さえ越えたというのに、あまりにこともなげな移動なので、ここに降り立ったのはとりあえず私の体だけだ。まわりにある風景や人の声を包んでいた薄い膜がほどけ、この地の熱で脇の下を汗がつたわり始めるころ、やっと意識が追いついてくる。シートベルトに縛られ、窓からはるか地表を見下ろしている私の体が雲の峰の上やそのふもとを飛んでいるとき、意識は、地表を擦過するフライトの影を追うように陸路を連いてくる。そして国境のあたりで何かに引っかかり、そのままぐずぐずと追いついてこなかった。
カオイダン難民キャンプ、JVC、難民定住調査員……カンボジア難民と向かい合い、クメール人の眼に囲まれて過ごしてきた時間が胸のどこかで疼きのように頭をもたげる。
難民問題にかかわることをやめ、バンコクの喧騒と猥雑のなかにもぐることを選んでしまった私にとって、アンコールやプノンペンはいつまでも遠かった。
カンボジアの首都プノンペンも、そしてアンコールの遺跡たちも、ギクシャクしつつではあったがずいぶん早い時期から訪問が可能になった。が、その当時でもタイとの国境には数十万のカンボジア難民がキャンプの中で暮らしていたし、もっと多くが第三国へ逃れていった。そしてさらに多くが物言わぬ骸となった。
アンコールやプノンペンに観光で訪れることには何の興味も抱けなかったし、難民にかかわることで二十代を過ごした自分が、禿げ上がった頭、しかつめらしい顔で遺跡のなかや観光地を歩いているという、頭のなかに浮かぶ戯画めいた光景も怖かった。
なんの具体性も方向性も持たないまま、やり過ごすだけやり過ごしてきた年月に突然のように句読点が打たれる。
シェム・リアップの町は、舗装してあるのやらないのやら、どこから舗装が始まり、いつの間に赤土だけの道に変化したのかわからないような道路が多い。町を貫く国道や川沿いの道を外れると、家々や樹々は赤い土ぼこりをかぶるままに放置され、午後の陽光を受けながら、一日の盛りを過ぎた暑熱のなかにたたずむ。
ワット・ボーという寺の敷地のなかに入り、やはり土埃にあせた目立たぬ垣根の向こうへ踏み込むと、斜めに傾いた低い軒下の奥に踊りの稽古をのぞき見ることができる。午後の三時を過ぎたころから、農作業の手伝いや子守り、物売り、学校を終えた子供たちが集まってくる。鏡の前で稽古着に着替えつつ、子供ながらに、その日一日の生活が自分にもたらしたものをはぎ落とす努力をして、彼らはボラン女史の前に立つ。ボラン先生は彼らの荒れた手や爪、黒ずんで皮膚が硬くなったくるぶしなどは見て見ぬふりをし、ひざや持病の痛みをこらえて子供たちの列を整え、楽器の準備ができると彼らに向かって横座りする。手には短い一本の小枝。時折、先生は演奏を止めさせると自ら立ち上がり、子供たちに足の運びや型、腰や手の動きを指導する。気を抜いていると先生の手は一振りされ、小枝が子供たちの四肢の上で弾けるような音をたてて容赦がない。しかし打たれた子供たちの顔には、ほんの一瞬驚きの表情が過ぎるだけだ。まだ小学校に上がらぬと見える年ごろの子でさえ、痛いという素振りも、ましてやベソをかいたり膨れっ面をしたりということもなく、一瞬ののちには態勢を整えにかかる。
名もないこの教室が開かれて八年、観光客の依頼を受けて踊るようになり、見出されてパリ公演に招かれるまでになった。最初は慎ましやかなコーヒーショップの土間にビニールシートを敷いただけの稽古場だったそうだ。日本のNGO「アプサラプロジェクト」の支援などを受けつつ、板壁を継ぎ足し、やっとタイル敷きの床になり、つい最近になってどうやら便所も出来上がった。とはいえ、破れ屋ともいえる外見からは、そのなかにある音楽や舞といった詩的なものは絶対に見て取れない。楽器類はすべてぼろぼろといっていい中古品だし、土地も寺からの借りものだ。
ボラン先生自身はプノンペンの芸術大学舞踊学科を出て、国立舞踊団の一員として長年踊った。被害者にも加害者にもならないということが不可能で、嵐を避けるためには被害者でも加害者でもあるという灰色の地点で従うしかなかったであろうポル・ポト政権の恐怖政治時代には、無為無言のままその身分や経験をひた隠しにして生き延びた。戦後はプノンペンには戻らず、この地で伝統舞踊の伝承にすべてを賭けて、無料で子供たちにレッスンする毎日だ。
昔のカンボジアでの踊り子たちは上流家庭の子弟が多く、その意味では身体的にも心理的にも健康だった。緩やかに続く永い緊張を強いられる独特の舞いは健康でしなやかな身体を要求する。
「けれどもそれをこの子たちに望んではいけません。家の手伝いや家計を助けるために働かねばならない子たちです。水仕事さえ手の美しさを損なうのですから、本当は……ねえ」
ボラン先生は自分の手を見ながら言う。その手へこちらが目を向けていることに気づくと苦笑して隠してしまう。舞踊団の踊り子の手から隷民の手へと削られていった、若いころの経験を隠すかのように。昔は手首から上へ反らせたその指の先が、ちょっと押してやればそのまま孤を描いて自分の腕の背にくっつくほどしなやかだったが、いまは試みる気もしないと言う。慢性で痛む膝はながく立っていることに耐えられない。彼女の老いは老いだけがもたらしたものではない。だからこそ、永い戦火のうちに、同族相食むなかで荒んでしまったものにいまいちど息吹をこめようと思い立つしかなかったのではないか。文化、伝統を担う自負にあふれた舞手の、失われた時の奪回戦はいまようやく緒についたばかりだ。
ここで学ぶ子供たちはいま、ロイヤルダンスを基本とする古典舞踊を学び、伝統的な農村の踊り、ラーマーヤナ物語、アプサラの舞などレパートリーも広くもつようになった。町なかにある劇場兼レストランで定期的な舞台もある。稽古がすむと一斉にその舞台への準備が始まる。楽器類をまとめて運び出す者、衣装をクローマーに包む者、大人たちも忙しく指示を出し、いつの間にやらおんぼろのバンが稽古場の前に現れ、皆が乗りこむのを待っている。
さっきまでちらちらと客の存在を気にしていた子供たちもあわただしく更衣室に消え、化粧をしなくてはならない少女たちだけが鏡の前に座り込む。鏡をのぞきこむ目はもう決してこちらの方を見返りはしない。一心の化粧と集中。少女同士で語られてしかるべき、幼い、あるいはたわいのない、そのような会話さえまったくなくなる。眉がひかれ、アイシャドウが濃い影をつくり、頬に紅がうたれる。太陽はもう森の向こう、トンレサップ湖を輝かせて地平へ沈んだ頃だ。いつのまにか青白い蛍光灯がついて、屋根裏に張った蜘蛛の巣を浮き立たせ、羽虫を呼び寄せ始める。化粧を終えた少女は両膝で立ち、鏡のなかの自分の姿をじっと見つめながら背すじを伸ばすと、指をひらりと使って腰や胸の衣装の線を直す。こどもから娘へ、ただの人から舞姫へ、いつとは知れず変身を遂げている。ふと見ると、そのかたわらの柱には花の輪がいくつかかけられている。そばに寄れば香ばしいはずの、その花弁だけをちぎってつなげた薄黄色の輪。
カンボジアの舞にまず無条件に求められるものは若さではないのかと思えてならない。インドシナ半島に広大無辺の領土を築いたアンコール帝国。若く壮大で尽きない精力を猛らせたこの帝国は、その中心にシバ神の陽根アンコール・ワットを屹立させ、花を花として、その花びら、花弁の美しさ、最も目立つ美を発するその核のみを執拗に蒸留して愛でようとしたのではないか。そして生まれたのがこの舞姫たちなのだ。石工たちは、天に舞うといわれる舞姫「アプサラ」を刻み、地上の舞姫たちはそのレリーフを師とし範として舞う。その姿を見て石工がさらに彫る。神と人間との幸福な共同作業が鎖をつなぐように綿々と続き、石の壁を隙間なく飾った。それがアンコールの業だったのだ。そしていま、その業の余燼として、情を滲ませつづけるメディアとしての遺跡が私の前にある。その情が私の気をくじき、現代の舞姫たちは、舞に賭けるものの深刻さでさらに近づきがたい。彼女たちと同じ舞台を踏むときまであと数日。私たちの背に、それでも同じように月齢十三日の月は昇ってくるはずだ。(つづく)
|



![]()